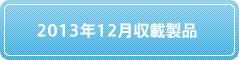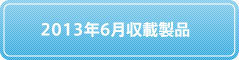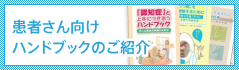QPバックナンバー
2010.02.15
UP!
※執筆者等の所属は発刊当時のものです
各情報誌をご希望の方は弊社MRもしくは下記連絡先までお問い合わせください
■医療機関専用お問い合せダイヤル ![]() 0120-041189 (ヨイイヤク)
0120-041189 (ヨイイヤク)
TEL:06-6308-3366 FAX:06-6308-0334
E-mail:info-di@kyowayakuhin.co.jp
Vol.8 / 社会参加
2010年2月
2010年2月
●社会参加
京都大学医学部臨床教授
京都四条病院
パーキンソン病・神経難病センター
久野 貞子 先生
・可能な限り社会参加を
・「できなくなった」から「まだこれもできる」への思考転換
・まず本人が動く、そして家族も
・将来に期待が持てる新しい治療法
・まず専門医の的確な診断を
・活用したい公的支援や社会資源
京都四条病院
パーキンソン病・神経難病センター
久野 貞子 先生
・可能な限り社会参加を
・「できなくなった」から「まだこれもできる」への思考転換
・まず本人が動く、そして家族も
・将来に期待が持てる新しい治療法
・まず専門医の的確な診断を
・活用したい公的支援や社会資源
Vol.7 / 手を使う
2009年11月
2009年11月
● 手を使う
公立大学法人福島県立医科大学
医学部神経内科学講座教授
宇川 義一 先生
・よーい、ドン!の話
・「硬くて遅い運動障害」と「柔らかくて早い運動障害」
・手の動きに発現する症状
・筋固縮の予防にも役立つリハビリテーション
・注目される反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)療法
・できる限り自分で。メガネ(治療法)はいろいろ
医学部神経内科学講座教授
宇川 義一 先生
・よーい、ドン!の話
・「硬くて遅い運動障害」と「柔らかくて早い運動障害」
・手の動きに発現する症状
・筋固縮の予防にも役立つリハビリテーション
・注目される反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)療法
・できる限り自分で。メガネ(治療法)はいろいろ
Vol.6 / 抑うつ
2009年6月
2009年6月
● 抑うつ
東海大学医学部内科学系神経内科教授
吉井文均先生
・非運動症状のひとつ、抑うつ/4割が経験
・質の異なる抑うつ症状/アプローチに注意
・コミュニケーションを通して知る/症状の背景
・大きく変わったパーキンソン病のとらえ方/非運動症状に焦点
・症状の相関性をみながら進める治療/複雑に絡む症状
・音楽療法の効果、「場」の効用/高い満足度
・大切な抑うつ症状への配慮/一緒に取り組む
吉井文均先生
・非運動症状のひとつ、抑うつ/4割が経験
・質の異なる抑うつ症状/アプローチに注意
・コミュニケーションを通して知る/症状の背景
・大きく変わったパーキンソン病のとらえ方/非運動症状に焦点
・症状の相関性をみながら進める治療/複雑に絡む症状
・音楽療法の効果、「場」の効用/高い満足度
・大切な抑うつ症状への配慮/一緒に取り組む
Vol.5 / 話す
2009年3月
2009年3月
● 話す
愛媛大学大学院医学系研究科病態治療内科
附属病院創薬・育薬センター長
附属病院神経内科・創薬治療内科教授
野元 正弘 先生
・失語症と異なる「構音障害」
・まず手足に、そして声に
・薬物による治療と訓練による治療
・毎日の生活のなかで
・病気だからこその役割
附属病院創薬・育薬センター長
附属病院神経内科・創薬治療内科教授
野元 正弘 先生
・失語症と異なる「構音障害」
・まず手足に、そして声に
・薬物による治療と訓練による治療
・毎日の生活のなかで
・病気だからこその役割
Vol.4 / 眠る
2008年8月
2008年8月
● 眠る
財団法人操風会岡山旭東病院
神経内科主任医長
柏原 健一 先生
・睡眠障害と覚醒障害ー現れ方に特徴もー
・睡眠のリズムを壊すさまざまな要素ー一番はトイレの問題ー
・大切な薬の調整ー主治医とのコミュニケーションー
・一日のリズム作りー昼間は動き、夜はしっかり寝るー
・とにかく前向きにーやりたいことを探すー
神経内科主任医長
柏原 健一 先生
・睡眠障害と覚醒障害ー現れ方に特徴もー
・睡眠のリズムを壊すさまざまな要素ー一番はトイレの問題ー
・大切な薬の調整ー主治医とのコミュニケーションー
・一日のリズム作りー昼間は動き、夜はしっかり寝るー
・とにかく前向きにーやりたいことを探すー
Vol.3 / 食べる
2008年2月
2008年2月
● 食べる
独立行政法人国立病院機構相模原病院
神経内科医長
長谷川 一子 先生
・嚥下障害は自覚に乏しく、誤嚥の原因に
・誤嚥に伴う肺炎は極めて危険
・咳き・むせには要注意
・食事は食べやすいように工夫する
・まずはご家族や医療スタッフとの楽しい会話が重要
・症状が進めば胃瘻も
・おいしく食べてQOLの向上を
神経内科医長
長谷川 一子 先生
・嚥下障害は自覚に乏しく、誤嚥の原因に
・誤嚥に伴う肺炎は極めて危険
・咳き・むせには要注意
・食事は食べやすいように工夫する
・まずはご家族や医療スタッフとの楽しい会話が重要
・症状が進めば胃瘻も
・おいしく食べてQOLの向上を
Vol.2 / 歩行障害
2007年9月
2007年9月
● 歩行障害
和歌山県立医科大学神経内科教授
近藤 智善 先生
・パーキンソン病の歩行障害の特徴
・ドパミン作動性治療抵抗性のすくみ足と姿勢反射障害を伴う歩行障害
・歩行障害がある患者への歩行開始時のアドバイス
・パーキンソン病の歩行障害の治療方針
・QOLを改善・維持するための工夫
・QOLを改善・維持するための生活指導
近藤 智善 先生
・パーキンソン病の歩行障害の特徴
・ドパミン作動性治療抵抗性のすくみ足と姿勢反射障害を伴う歩行障害
・歩行障害がある患者への歩行開始時のアドバイス
・パーキンソン病の歩行障害の治療方針
・QOLを改善・維持するための工夫
・QOLを改善・維持するための生活指導
Vol.1 / QOL維持のためのパーキンソン病ガイドライン活用
2007年5月
2007年5月
●QOL維持のためのパーキンソン病ガイドライン活用
順天堂大学医学部特任教授 老人性疾患病態治療研究センター長
水野 美邦 先生
・QOLを維持するためにPDガイドラインを活用する
・早期PDから長期のQOLを考慮した薬剤選択が必要
・進行期はPD症状と副作用の発現を観察しながら薬剤の選択を考慮する
・PDは長期にわたる疾患であることを念頭におき、患者背景を考えた診療をする
水野 美邦 先生
・QOLを維持するためにPDガイドラインを活用する
・早期PDから長期のQOLを考慮した薬剤選択が必要
・進行期はPD症状と副作用の発現を観察しながら薬剤の選択を考慮する
・PDは長期にわたる疾患であることを念頭におき、患者背景を考えた診療をする
情報誌紹介